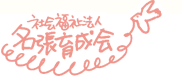- HOME
- ニュース
名張育成会こどもグループ(児童デイサービスどれみ、なちゅ、ゆぅら、児童寮、ぱれっと)では3年前より、名張育成会特別事業顧問の久保義和先生を講師に迎え、発達支援に関わる地域の方を対象に、公開講座を開講してきました。
昨年度までは、「発達障害実践講座」として、発達障害がある子どもを理解し、支援を行うために、障害特性や心理検査について学んできました。
今年度は「神経心理学Ⅰ」と題し、脳科学や神経心理学の学習を通して、人間理解を基に発達障害がある子どもの支援を考えていくために、講座を開講しました。
年間9回、61名の受講生と共に1年間、神経心理学について学んでいきたいと思います。
11月16日「症状から見た脳機能について~失語~」
今まで学んだ内容を基礎とし、症状から脳機能について考える講座が始まりました。今回は、失語の症状を通して、脳機能について学びました。
失語は代表的な分類として、ブローカー失語やウェルニッケ失語が一般的な分類ですが、今回の講座では、①言葉を使って話すことの障害(言葉を言うことの失敗)と、②話すことそのことの能力の障害()言葉を選択することの失敗)、の2つに分類し、臨床的な状態像から、応用を学びました。一般的な失語症の捉え方とは違ったため、言葉の1つ1つが難しく、またイメージが持ちにくいこともありましたが、久保先生は丁寧に解説して頂きました。
私たちが支援している子どもたちは、言葉でのコミュニケーションが苦手であり、その苦手さを出来るように指導・訓練する場合もありますが、今回の講座で学んだ失語症の症状を通して、言葉やコミュニケーションを司る脳機能の部分の未熟さがある子ども達であることが分かりました。1つ1つ子ども達の困難さを理解していくために学びを進めていきたいと思いました。
10月19日「神経心理学とは何か?」
今年度開催している、神経心理学Ⅰは、“人間理解”をするために“脳”について理解し、“人”にについて深く考え、支援について考えることが目的です。久保先生は、神経心理学を学ぶ私たちにとって、“脳”の機能は複雑である印象があるので、理解を促すために前回の講座内容を確認しながら、講座を勧めて頂いています。今回の講座では、脳は脳を持つ人のために働くことや脳には説明出来ない可塑性を柔軟性があるといこと、脳の未熟さなどを再度確認した上で、脳科学の基礎知識③では、大脳辺縁系と視床について学びました。
大脳辺縁系は、様々な研究の中から、偶然に脳幹周辺を取り巻く共通した構造があることが発見され、以降の研究で環境に対する適応能力や情動をコントロールする、記憶の回路があるなど研究の流れから、様々な機能が考えられてきた経緯を、また視床は、感覚の中継所、また情報の選択に関係していることを教えて頂きました。今回の講座は、“脳”機能について難しく捉えるのではなく、1つずつ復習をしながら久保先生と一緒に学んでいきたいと思いました。
9月2日「脳科学の基礎知識④」
今回の講座では、前回学んだ大脳辺縁系が、情動のコントロールする、海馬に象徴される記憶の回路であること再度確認した後、大脳辺縁系が担う機能は、人の行為、行動に関係した領域であることから、大脳辺縁系と社会的なコミュニケーションとの関係について学びました。
社会的なコミュニケーションの根本的な部分は、情動であり、その情動の表出の在り方は人間の進化から、読み取れると教えて頂きました。その上で、情動における大脳皮質や脳幹、自律神経系の働きについて繰り返し、お話されていました。
発達障害がある子どもに見られる、社会的なコミュニケーションの困難さを理解するために、私たちは、神経心理学を学び、支援に具体性を持たせ、原因を推測し、支援に活かすことであるとが大切であると思いました。
7月20日「脳科学の基礎知識③」
今年度開催している、神経心理学Ⅰは、“人間理解”をするために“脳”について理解し、“人”にについて深く考え、支援について考えることが目的です。久保先生は、神経心理学を学ぶ私たちにとって、“脳”の機能は複雑である印象があるので、理解を促すために前回の講座内容を確認しながら、講座を勧めて頂いています。今回の講座では、脳は脳を持つ人のために働くことや脳には説明出来ない可塑性を柔軟性があるといこと、脳の未熟さなどを再度確認した上で、脳科学の基礎知識③では、大脳辺縁系と視床について学びました。
大脳辺縁系は、様々な研究の中から、偶然に脳幹周辺を取り巻く共通した構造があることが発見され、以降の研究で環境に対する適応能力や情動をコントロールする、記憶の回路があるなど研究の流れから、様々な機能が考えられてきた経緯を、また視床は、感覚の中継所、また情報の選択に関係していることを教えて頂きました。今回の講座は、“脳”機能について難しく捉えるのではなく、1つずつ復習をしながら久保先生と一緒に学んでいきたいと思いました。
6月15日「脳科学の基礎知識②」
今回の講座では、前回の復習である、基本的な人間の脳の特性について再度、お話頂いた後、脳科学の基礎知識②では、各前頭葉と頭頂葉の領野について学びました。
私たちは、脳科学を学ぶ時、脳の各部位の名前や働きについて覚えようとしますが、久保先生は名前を覚えるのではなく、発達障害がある子どもたちに対する理解をするために、脳科学を学び、彼らの困難さを生みだす原因としての脳の特性を学ぶことが大切であると繰り返しお話されていました。脳は、脳自身の脆弱性を補うため、また脳を持つ「人」を守るシステムがあるため、まだまだ脳機能自体が解明されていない部分が多いことも学びました。
今後、講座では子どもたちが見せる行為・行動から脳科学を通して、理解、支援方法について学んでいきますが、難しく捉えるのではなく、目の前にいる子どもたちのより良い支援者になるべく、学んでいければと思いました。
5月18日「脳科学の基礎知識①」
今回の講座では、脳科学、つまり、脳の名称や機能について学ぶことではなく、脳の基本的な特性を理解することで、支援する人たちを理解することが目的であることをおさえた上で、脳科学の基礎知識①では、基本的な脳の特性について学びました。
私たちは、生物の中で人間の脳が一番優れていると思いがちですが、基本的に人間の脳は①未熟・未完成であり、「余裕」がない、②脳は脳を持つ人のためにだけ働くこと、つまり、脳は脳を持つ人を「守る」、③人が見せる行為・行動は環境や変化に適応するために脳が行っている、という特性があると教えて頂きました。脳の特性から、私たちが支援している発達障害がある子どもや人を見ると、脳の脆弱性がある中、適応しようとしている姿があり、その姿を私たちは「多動」や「自分勝手」など、様々な言葉で誤解をしているのではないかと思いました。
これから講座を通して、「人」を深く理解し、支援する方法について学んでいきたいと思いました。